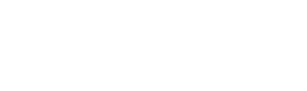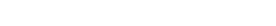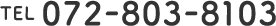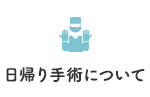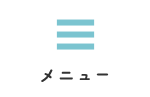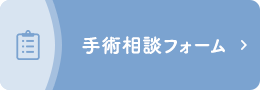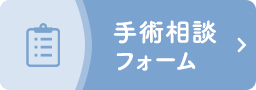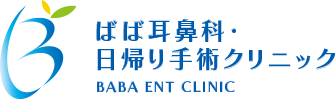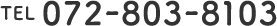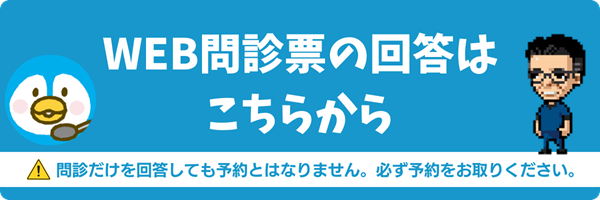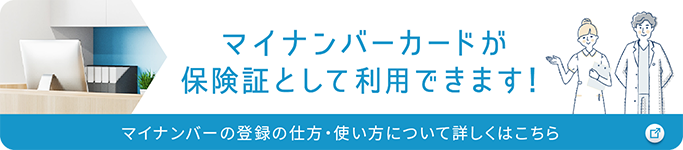こんにちは。ばば耳鼻科・日帰り手術クリニックの院長、馬場奨です。
今回は当院でもご相談をいただくことがある、鼻の手術後に起こる「エンプティノーズ症候群」(Empty Nose Syndrome, ENS,空鼻症候群)について解説できればと思います。
エンプティノーズ症候群(ENS)は、鼻の手術、特に下鼻甲介(かびこうかい)の手術を受けた後に、下鼻甲介が過剰に小さくなった際に起こることがある、まれな病気です。これは、鼻の中の組織が大きく減ってしまった状態のことを指します。
エンプティノーズ症候群についての基本的な解説
エンプティノーズ症候群はどんな症状がでるか?
ENSの患者さんは、「鼻が詰まっている感じがする」という不思議な感覚を持ちます。でも実際には、鼻の空間は広くなっているのです。
具体的には、こんな症状が出ることがあります。
- 鼻の乾燥感
- 目鼻内に空気が流れているのを感じない
- 息苦しさや呼吸のしづらさ
- 鼻内が開きすぎている感覚
- 鼻内のごみ(鼻垢)が多く溜まる感覚
- 鼻内が焼ける、顔が痛む感覚
心や生活への影響
ENSは、生活の質(QOL)を大きく下げることがあります。よく眠れなくなる、集中力が落ちる、不安を感じやすくなる、など精神的な影響を受ける人もいます。
治療方法は?
現在、ENSの治療は保湿スプレーや薬などの保存的治療が中心です。最近の研究では、手術で鼻の中の形を整えることで、長期的に症状が改善する可能性があることがわかってきました。
エンプティーノーズ症候群の概要まとめ
ENSは、鼻の手術後に起こることがある病気で、「鼻が詰まっている感じがする」のが特徴です。鼻が広くなっているのに、息がしづらくなるという逆説的な症状が現れます。さらに、生活やメンタルヘルスにも影響を与えることがあるため、適切な治療が必要です。最近では、手術による治療法も研究されており、今後、症状を和らげる方法が見つかる可能性があります。
医療提供者である私達は、ENSを起こさないような手術治療を追求していくことが最も大切でしょう。
エンプティノーズ症候群(ENS)の病因:3つの主要な要因
エンプティノーズ症候群(ENS)は、鼻の手術後に発生することがある病気で、鼻の空間が広くなっているのに息苦しさや違和感を感じるのが特徴です。この症状の発生には、①鼻の構造の変化による気流の乱れ、②鼻粘膜の機能障害、③神経の感覚低下、の3つの要因が関係している、と最近の研究(2024年まで)で報告されるようになってきました。
以下は少し専門的な内容となってしまいますが、ご興味のある方はお読みください。
① 解剖学的な鼻甲介構造の変化による気流の乱れ
下鼻甲介の役割とENSでの変化
鼻の中には下鼻甲介(かびこうかい)という組織があり、これが空気の流れを適切に調整し、加湿・加温を行う重要な役割を果たしています。しかし、ENS患者では、手術後にこの下鼻甲介が過度に変形もしくは小さくなってしまい、鼻の形と空気の流れ(気流動態)が大きく変化します。
気流のバランスの崩れ
研究によると、ENS患者では、下鼻道(かびどう)を通る空気の量が減り、中鼻道(ちゅうびどう)を通る空気の量が増えるという逆説的な現象が起こっています。本来なら広くなった空間には空気が流れやすくなるはずですが、ENS患者では気流のバランスが崩れ、鼻の奥へ空気が適切に流れなくなっているのです。この変化によって、呼吸の違和感や息苦しさが生じると考えられています。
壁せん断応力(Wall-Shear Stress, WSS)とシアフォース(Shear Force)の低下
•WSS(壁せん断応力):鼻の粘膜に対して空気が「押しつける力」。ENS患者では、気流が適切に分布しなくなるため、WSSが大きく低下し、鼻粘膜が適切な刺激を受けられなくなります。
•シアフォース(Shear Force):鼻の粘膜の表面を「なでるように流れる力」。ENSではこの力も減少し、鼻粘膜が空気の流れを適切に感知できなくなります。
ENSの患者では、このWSSとシアフォースの低下によって、鼻の粘膜が空気の刺激を感じにくくなり、「鼻が空っぽな感じがする」「息を吸っている実感がない」といった症状につながることが確認されています。
コアンダ効果(Coandă effect)の影響
コアンダ効果とは、流れる液体や気体(空気)が、近くにある曲がった表面に沿って進む性質のことです。
ENSの患者では、下鼻甲介な過度な変形、もしくは過剰に小さくなることで、コアンダ効果が低下する可能性が指摘されています。通常なら、鼻の内側のカーブに沿って流れるはずの空気が、ENS患者では一直線に進んでしまい、適切な気流の分散ができません。このため、空気の流れが不均衡になり、WSSとシアフォースがさらに低下する原因になっています。
そのため、ENSを予防するためには、手術の際に下鼻甲介を少なくとも50%は温存することを推奨する報告があります。これにより、空気の流れを適度に調整し、ENSの発症リスクを低減することができるといわれています。もし完全に切除すると、鼻の加湿・加温機能が23%低下することも報告されており、乾燥や不快感が強くなります。
② 鼻粘膜の機能障害(温度・湿度調節の問題)
鼻の粘膜は、吸い込んだ空気を適切な温度と湿度に調整する役割を持っています。しかし、ENSの患者では、下鼻甲介の過剰な減量によって粘膜の表面積が減少し、空気と粘膜の接触が減ることで、この調整機能が低下します。
鼻粘膜の変化
ENS患者では、鼻の粘膜が正常な状態を保てず、以下のような変化が起こることがあります。
•扁平上皮化生:鼻の粘膜が「皮膚のような状態」に変化し、機能を失う。
•粘膜下線維化:粘膜の下に硬い線維が増え、柔軟性が失われる。
•杯細胞の減少:粘液を分泌する細胞が減少し、鼻内の乾燥ひどくなり、加湿機能が低下する。
TRPM8受容体の減少
鼻粘膜には、TRPM8(トリップエムエイト、Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily M Member 8)という温度センサーがあり、冷たい空気やメントールに反応して「スースーする感覚」を生み出します。ENS患者では、下鼻甲介が過剰に小さくなることなどでTRPM8の数が減少し、空気を冷たいと感じる能力が低下します(鼻の粘膜を温めないといけないと産熱が促される機能も低下します)。
その結果…
•鼻の粘膜が適切に冷却されず、脳に「空気が流れている」という信号(温度調節の指令)を送れなくなる。
•脳から鼻へ血流や粘液の分泌を促す指令も減り、加湿・加温機能が低下する。
•WSSとシアフォースの低下がさらに悪化し、気流による適切な刺激を受けられなくなる。
③ 神経感覚の欠落(気流を感じる能力の低下)
三叉神経の働きとENS患者での異常
鼻の粘膜には、三叉神経という神経が分布しており、空気の流れや温度の変化を感じる重要な役割を果たしています。しかし、ENS患者では、手術の影響でこの神経の感覚が低下していることが研究で確認されています。
特に、ENS患者では、三叉神経の「TRPM8を介した冷感機能」が低下しているため、鼻を通る空気が「冷たい」「心地よい」と感じることができず、「息を吸っている実感がない」という症状につながっています。
ENS患者における神経感覚の低下の影響
•WSSやシアフォースが低下しても、脳がそれを感知できない
•気流の刺激を正しく感知できず、呼吸ができていないように錯覚する
•鼻の気流分布が乱れ、呼吸中枢への信号が適切に伝わらない
このように、ENSの症状は単なる鼻の構造の問題ではなく、粘膜の機能低下と神経感覚の低下が相互に影響し合っていることがわかってきました。
まとめ
ENSは、①鼻甲介の構造変化による気流動態の異常、②鼻粘膜の機能障害、③神経感覚の低下が複合的に関係して発症することがあります。
現在(2025年3月時点)、これらの機能を調べる検査はクリニックではまだ行われていませんが、今後の研究や技術の進歩によって、鼻の手術(特に下鼻甲介の手術)では、ENSを予防する方法がさらに工夫されていくと考えられます。
文責
ばば耳鼻科・日帰り手術クリニック 院長 馬場奨
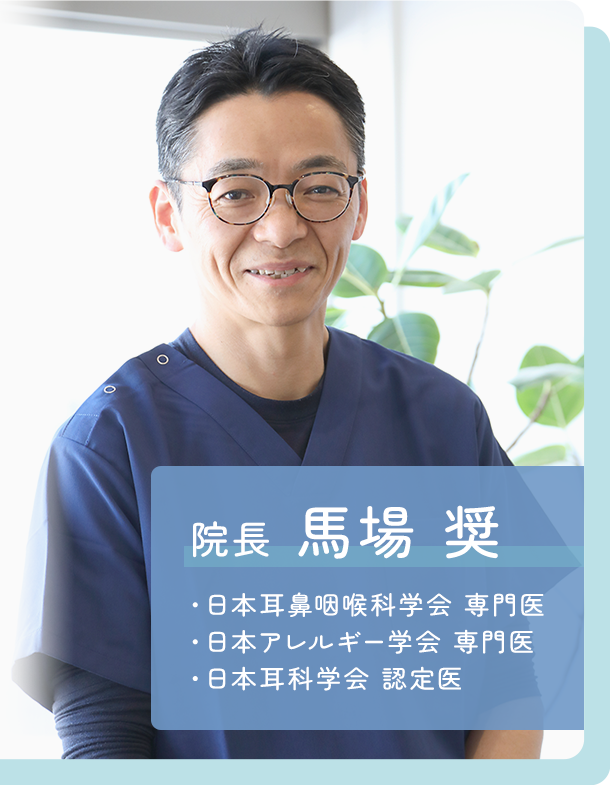 ・医学博士
・医学博士- ・日本耳鼻咽喉科学会 専門医
- ・日本アレルギー学会 専門医
- ・厚生労働省 補聴器適合判定医
- ・難病指定医
2020年9月にばば耳鼻科クリニックを開院。耳や鼻の日帰り手術の診療に力を入れ、可能な限りの完治をめざした治療に取り組んでいる。2024年10月には医院名を「ばば耳鼻科・日帰り手術クリニック」と改め、耳と鼻の日帰り手術に注力。また、常に患者の立場になり、各所にモニターを設置して「医療の見える化」を行っているほか、利便性の向上や診療の質を高めることにも注力している。